 彩の国いきがい大学東松山学園
彩の国いきがい大学東松山学園平成25年度28期課題学習発表・福祉環境科B班
 彩の国いきがい大学東松山学園
彩の国いきがい大学東松山学園
平成25年度28期課題学習発表・福祉環境科B班 ![]()
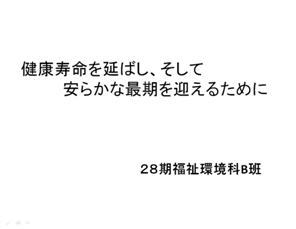 |
健康寿命を延ばし、そして
安らかな最期を迎えるために
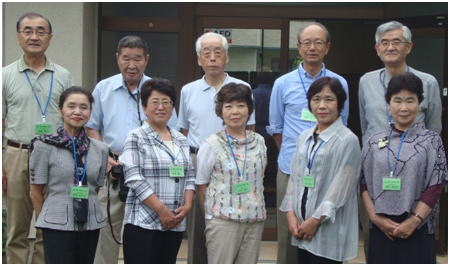 (担当)
(担当)
班長 須田雅次 :ウオーキング
写真 仲野健次 :食事
記録 奈良 勲 :介護・終末医療等
記録 根岸浩一 :運動と健康
編集 藤原 厚 :介護・終末医療等
総務 本保せつ子 : 介護・終末医療等
副班長 宮崎雪江 :食事
総務 山下富江 :運動と健康
会計 山口富子 :ウオーキング
会計 吉田多枝子 :介護・終末医療等
1.はじめに
二つのグループにわけて学習しました。ひとつのグループは、健康寿命を伸ばす方法について考えてみ
ました。いかに健康に生活できる期間を伸ばすか、について検討した結果、私達の願いでもある「健康で
長生きする=平均寿命と健康寿命の差を縮める」具体的方法について、「運動と食事」の面から考察し、
グループ全員で具体的に実施していくことにしました。
もう一つのグループは、介護保険・医療費の財政負担の増加が懸念されているのですが、実態はどうなっ
ているのか調査しました。また、介護が必要となった場合のこれまでの施設等に加えて、「サービス付き
高齢者向け住宅」がスタートしましたが、調査・見学をしました。
そして、終末期医療の問題点と生前の意思表示=リビング・ウイルについて考察しました。
2.介護保険の現状と見通し
①介護保険料の推移、②介護保険の仕組・財源、③被保険者の増加の推移、④介護認定者数、⑤介護
保険給付額・今後の予想。詳細は冊子をご覧下さい。75才以上からの生活がカギです。
介護保険の実態を理解すると、行政が「介護予防の推進」として運動教室の開催等、様々な予防事業を推
進していることが、よく理解出来ます。自分の健康維持が、自分自身の幸せだけでなく、社会のためにも
重要なことであると再認識し、健康寿命を延ばす努力をするため行動をとりたいと思います。
3.運動と健康
高齢者が健康状態から介護を必要とする状態になるうちの多くは、転倒等による骨折から筋力の低下を
招き、活動が抑制されることによると言われています。転倒を防ぐための筋力を保ち、バランス機能を維
持するための方法の一つに健康体操が取り上げられています。
健康体操のねらいは、①下肢筋力の強化。②下肢関節の柔軟性を高める。③体幹の柔軟性・支持性の向
上。④敏捷性・協調性の向上。⑤バランス能力の向上などが考えられます。体操には様々なものがあり、
どれが一番効果があるのかと迷いますが、自分の体力・健康状態にあった運動で、楽しく続けられる運動
が一番良いと思われます。各自治体のおもな健康維持活動を調べ、特に富見市の活動状況については、富
士見市健康増進センター介護予防係の望月氏から講義していただけました。自分たちの住んでいる各市町
村がやっていることをまず把握し、参加し始めることが肝要だと思いました。
4.ウォーキング
 ほんの少しの時間とやる気さえあれば、ウォ
ほんの少しの時間とやる気さえあれば、ウォ
ーキングは今すぐに始められます。自分の健康
のために、また、健康で楽しく年をとるために
、私達はグループ全員でウォーキングに取り組
むことにしました。まず。東松山市役所嘱託ォ
ーキングインストラクターの奥野清歩先生を招
きし、ウォーキングの講義と実技指導をしてい
ただきました。
【実技指導の内容】
*靴の履き方 *ストレッチ
*良い歩き方
実際にメンバーで、「チャレンジ 一日一万歩」目標に、5月・6月の2か月間、毎日ウォーキングを行
い、ほぼ全員目標を達成しました。
また、各メンバーから、自分の住んでいる地域でおすすめのウォーキングコースを各自1コース、提出し
てもらいました。
5.食事
①人は食欲から老化すること ②健康常識は若い人と高齢者では異なること
③筋肉こそ健康長寿のキーワード ④多様な食品の摂取をする 「食の多様性スコァ」
 旬の食材を使った調理実習
旬の食材を使った調理実習
旬のものは、他の時期よりも新鮮で日光をび、栄養をしっか
りと蓄え、あるいは餌をたくさん摂り、その食材が最も美味し
く食べられる時期です。
わが国では「初物を食べると75日寿命が伸びる」などといわ
れ珍重されています。例としては、初鰹や早春の筍などがあげ
られます。そこで、筍や鰹、春キャベツなどの食材を使った食
事作りをしました。
5月22日の課題学習日に、松山市民活動センターの調理室を
借りて調理実習を行いました。
6.自宅での生活が難しくなった時
介護が必要となった時の施設のうち、今回は、2011年10月国交省、厚生労働省の共同所管により制度化
された「サービス付高齢者向け住宅」について、調べ見学しました。
居住権が重視されるように改正になったことで、利用者側に安心が伴なったと言えます。
しかし、厚生労働省、国土交通省の2つの省庁、老人福祉法、介護保険法、高齢者住まい法の3つの法律に
より規制されているとはいえ、営利目的の施設になるわけなので、受けられるサービス、住居の基準、支
払う費用等の契約内容については、じっくり比較検討する必要があります。
7.高齢者の医療費の現状とリビング・ウイルの必要性
厚生労働省は、近年の医療費の伸びの要因分解をすると、「高齢化」で1.5%前後、「医療の高度化」で
1〜2%前後の伸び率となっており、合わせて3%前後の伸びとなっていると見ています。この状態で2020
年には国民総医療費が47兆円、2025年50兆円に、高齢者医療費は現在13兆円が24兆円になると予測され
、人数の増加に加え一人当たりの医療費も増加しています。
① 年令別一人当たり医療費
各年齢別の人が、一年間にどのような治療を受けその医療費が幾らになっているか把握出来るようにな
っており、その集計を基に、人生の平均寿命の計算と同様の考えから計算すると、現在「生涯医療費」は
、理論値2,400万円と推計されています。生まれてから69才までの69年間の医療費と70才から亡くなるま
での医療費総額と、ほぼ同額と推計されています。
② 終末期医療
「延命治療」に関するアンケートは、どんな調査でも、望まないとするものが大多数です。救急医療の
発達した日本では、命を救おうと最大限の努力がなされ、人工呼吸器がつながれ、点滴で水分と栄養が補
給されるので、いつまでも生き続けられます。
本人が望まないのに、なぜ無理やり延命させられるのか? 我が国の医療は尊厳ある生命を出来る限り維持す
ることを至上命令としており、社会や法律も要求しています。延命治療の中止は、現状では医師が法律で
罰せられことになりかねません。無駄な延命治療を止めることが出来るのは、たった一つだけ患者自身が
延命治療の中止を望み其の意思が表明されている場合に限られています。リビング・ウイル「終末期の医
療・ケァについての意思表明書」です。
最近、「自然死」「平穏死」とか医療を遠ざけた死を推奨する本が、医師から出されています。医療が
残念ながら「安らかな死」を妨げていると述べられています。治ることが期待できない高齢者には、治療
より「生活の質や症状の緩和を優先させる」と言う指針も、医学会から提起されています。貴重な国民医
療費は、無駄な延命治療のためではなく、これから日本を背負って立つ若い人のために使って欲しいと、
心から思います。
③ リビング・ウイル「終末期の医療・ケァについての意思表明書」
日本では、1976年に「尊厳死協会(当初は安楽死協会)」が、発足し「尊厳死の宣言書(リビング・ウイ
ル)」に署名・会員登録、この協会が原点となっており、その会員は12万5千人おられます。しかし、法的
な裏付けはなく、大きく拡がっていません。アメリカでは、リビング・ウイルを国民の41%が表明し、日
本ではわずか0.1%に過ぎないと言われています
8.おわりに(まとめとして)
今後、高齢化が進んでいく中で、医療と介護の保険料が年々あがり、高齢者の医療費を現役世代が支え
る制度の分担金が増えていくことにより、現行の制度が大きく揺らぐことも懸念されます。私達は、医療
・介護の財政状況等を理解し、将来世代を気遣う思いやりを持った行動が必要であります。今回の学習を
通して、介護保険料は介護認定者数が増えることにより上がり、そこから、少なくとも「高齢者は健康で
いること自体が社会貢献となる。」ということを学びました。私達高齢者は、「健康を保ち、長生きした
い--。」そんな願いを持つ自分の健康維持が、自分自身の幸せだけでなく、社会のためにも重要なことで
あることを認識し、健康寿命を延ばすための努力をすることとしました。
copyright©2011 Higashimatsuyama Gakuen all rights reserved.